
(1)月10時間稼働 15万円 / (2)月20時間稼働 29万円 / (3)月30時間稼働 40万円 ※一例
・月30時間以上は別途問い合わせ
・訪問時の交通費は別途請求
・移動時間が発生する場合、往路のみ稼働時間
想定されるご依頼内容と凡その稼働時間
| アイデアを製品化するためのアドバイス | 10H |
|---|---|
| 製品開発の問題点にたいするアドバイス | 10H |
| 量産化に向けた試作機器のブラッシュアップ | 15H |
| 製品コスト削減のアドバイス | 10H |
| 製品小型化のアドバイス | 20H |
| 最適な設計外注の紹介、打合せ同席 | 5H |
| 販売のための必要な認証試験の調査、試験の段取り | 20H |
| 生産方法の検討、量産工場の選定 | 20H |
| 量産製造の段取り | 30H |
| 特許の調査 | 20H |
コスト削減
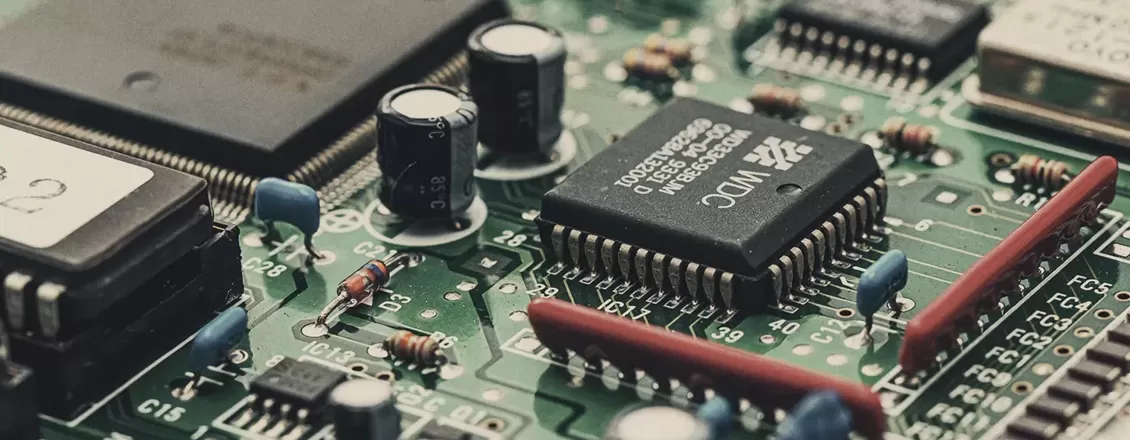
ものづくりにおけるコストの削減とは?
ものづくりにおけるコスト削減は、すべての企業で重要な経営課題です。しかし、ものづくりで行うコスト削減は、オフィス等でおこなわれるそれとは異なります。一時的なものではなく、長期的に利益となるような方法で削減を行えるよう、ものづくりにおけるコスト削減についてご紹介します。
-
1. ものづくりのコスト削減とは?
まずは、コスト削減の基礎知識について説明します。
1-1. コストの発生はいつ決定する?
コストが実際に発生するのはものづくりを行う「製造」の時点ですが、どれほどのコストが発生するのかが決まるのは、モノの「企画、設計」の段階です。実際は、製造よりも前の時点でコストの発生の多くが決まってしまうと言われており、それ以降のコスト削減は、「企画、設計」の段階よりは削減の余地が少ないと言われています。つまり、大幅なコストの削減を行うには、「企画、設計」が決まるより以前の時点で、知識を集めてコスト削減の方法を検討しなければなりません。
-
2. 削減しやすいコストとは
「企画、設計」とは別に、日ごろのものづくりにおいて発生するコストの中にも、削減可能なコストは色々あります。とくに削減のしやすいコストは、モノの製造には直接関係しないコストです。逆に、モノの品質を維持する部分、運営上必要不可欠な費用については、コスト削減が難しいと言えます。削減しやすいコスト
とは、たとえば、以下のようなコストが考えられます。2-1. 光熱費
光熱費の中でも、とくに効果を得られやすいのは電気代です。昨今話題となっている電気代の高騰ですが、照明を使用しない時はこまめに電源を切ること、LED照明に変える等を検討しましょう。電気を使う量が多く想定されるものづくりにおいて、電気の使用ルールの見なおしは大きな効果を発揮する可能性が高いでしょう。
2-2. 消耗品
マスクや梱包材、清掃道具等の消耗品は、それぞれを可能な限り安価なものにすることで、ある程度の削減効果が見込めます。
2-3. 通信費
インターネットの回線や社用携帯の維持費などは、使用実態に応じてプランの見直しを行い、運搬費や郵送料等のコストも、できる限り削減できるよう検討してみましょう。
-
3. ものづくりにおけるコスト削減の注意すべき点
では次に、コスト削減を検討する際の注意点をご紹介します。
3-1. 必要な投資は削減しない
「企画、設計」の段階で精査している事も考慮し、モノの品質や生産性を高める部分など、直接的に関わる費用は必要な投資として、削減の対象から外すようにしましょう。たとえば原材料をより安価なものに変えると、品質の低下を引き起こす恐れがあります。また設備投資費用や研究開発費用、広告宣伝費用などの削減は、一時的に削減効果を実感できるかもしれませんが、長い目でみるとマイナスとなってしまう可能性もあります。
3-2. コストの削減において、かなり背伸びした目標や無理な決まり事を作らない
コストの削減は、厳しくしすぎてしまうと息切れしてしまう可能性があります。従業員に大きなプレッシャーを与えてしまうと、モチベーションの低下や健康状態にも悪い影響が出てしまうことも考えられます。
-
4. コスト削減の効果を高めるには?
どのようにしたら、より効率的にコスト削減を行えるのでしょうか?
4-1. 協力体制づくりに尽力する
コスト削減で高い効果を得るためには、ものづくりに関わる全ての人の協力が必要です。「コスト削減を行う必要性や背景」「コストを削減し得られるメリット」等を説明し、理解してもらうことが大切です。
4-2. 職場の環境を整える
日ごろから、道具の収納場所を決めておく等の整理整頓、清掃によって、ものづくりの環境を意識的に整えておくことが大切です。整った環境作りによって、余計なコストの発生を防ぎ、無駄な時間を省くことによって生産性や作業効率が高まるでしょう。
-
5. ものづくりにおけるコスト削減の具体的な方法
最後に、ものづくりにおけるコスト削減の具体策をご紹介しましょう。
5-1. 無駄の解消で作業の効率を高める
・マニュアルを作成、適宜更新する
・材料や工具の置き場が作業する場所と離れている場合、取りに行く手間と時間を減らすため、置き場を再検討する
・数種類の部品や工具が同じ場所に置かれている場合、探す時間を省くためにひとつ一つ区別するさまざまな工具や部品が必要になることも多いものづくりにおいて、こういった改善を行うことは、作業効率を高めるだけでなく、ミスや事故を防ぐことにもつながります。しかしこういった細かな改善点は、管理側からは見つけにくく、作業する人の日々の気づきによって改善が可能となることも多いでしょう。ほんの少しの改善でも、積み重なると非常に大きな効果を生み出せるのです。
-
6. まとめ
コストの発生は、「企画、設計」の段階から、実際のものづくりの現場に至るまで、あらゆる点で行えるチャンスがあります。自分では気が付けなかった部分も、別の人物を通すとすぐに発見、見直しできることが多々あるかもしれません。モノづくりにおけるコストの削減に悩んでいる方は、「株式会社ファブナック」にお任せください。コストダウンなどを含めてさまざまなご提案をさせていただきます。
小型化
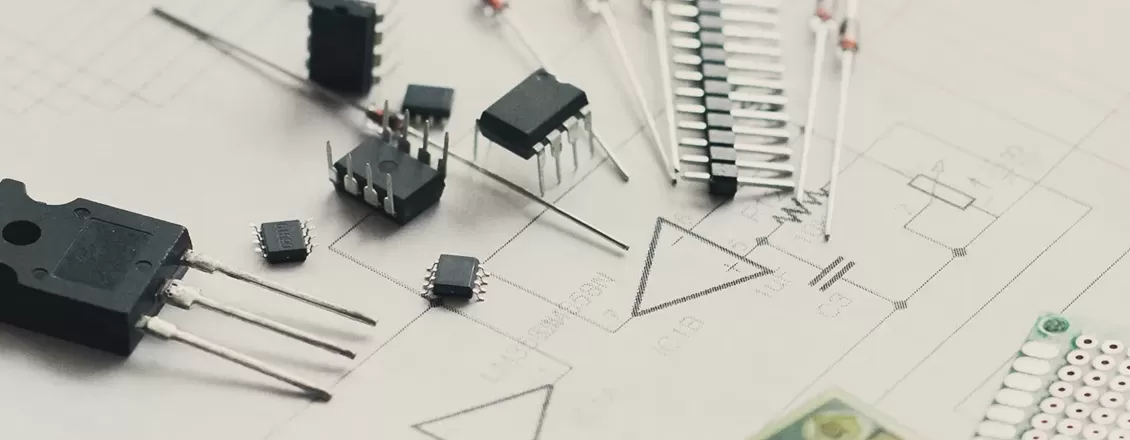
可能性が広がる!
パソコンやスマートフォンなど、「小型化」を実現することで、多くの人に受け入れられ、私たちの生活の質を向上させてくれた製品はたくさん存在しています。また、省エネ・省資源・省スペースなどを実現できる「小型化」は、昨今よく耳にする「持続可能な開発目標」の側面からも非常に関心の高い分野だといえます。ものづくりを「小型化」することによって、どのようなメリットを得られるのでしょうか。さまざまな側面からご紹介しましょう。
-
1. 小型化によるメリット
まずは、「省く」という側面から、小型化によるメリットをご紹介します。
1-1. 省スペース化
国土の小さい日本では、海外と比較すると工場や作業スペースが小さい傾向にあります。敷地を有効に活用できる省スペース化を図ることで、見た目をスッキリさせ、効率よく作業を行えるようになったり、できた空間に新たな設備を投入して効率をアップさせたりといったことが可能になるのです。
1-2. 省エネルギー化
世界的にも課題となっている省エネルギーは、モノが小型化することによって実現できます。機械を動かすといった直接関わるエネルギーの削減はもちろん、室内の温度や照明の明暗といった間接的な部分のエネルギーも削減が可能になります。環境問題に直結する省エネルギー化は、社会的価値の創出にも不可欠でしょう。
1-3. 軽量化
モノが軽量化すると、必要な設備自体の軽量化を図ることが可能です。さらに、輸送する際の費用も抑えられ、コストの削減や工数の低減にもつながります。
1-4. 資材の節約
モノが小型化することにより、使用される資材を減らせます。モノを作る際に必要な部品等の資材削減だけでなく、塗装や加工が必要な場合にはその塗料や、手間といった部分までも削減できるでしょう。
-
2. 小型化により実現できること
次は、小型化によって「新たな価値を得られる」という側面からメリットについて、ご紹介します。
2-1. 働きやすさ(効率化)につながる
モノを小型化することは、設備自体の小型化にもつながります。設備が小型化すると、作業のしやすさなど視認性があがり、風通しも良くなるでしょう。それにより、作業現場等の環境を改善し、作業の効率化につながるのです。
2-2. モノに新たな価値を付与する
モノが小型化すると、そのモノ自体の重量が減ることから、たとえば速く動かす必要のあるものや回転数を上げる必要があるものについて有利になるでしょう。また、熱を加えたり冷やしたりする際にも、モノが小さければ省エネルギーで、より早く効果を得られます。こうした特性を利用して、今までのシステムでは不可能とされてきた加工条件を付与でき、新たな価値を見出せる可能性もあるでしょう。
-
3. 小型化の必要性
さまざまな企業が製品の「小型化」を目指して、日々研究しています。では何故、「小型化」が必要なのでしょうか。
3-1. モノの可能性を広げられる
世の中のさまざまな製品が小型化されています。たとえば、パソコンや携帯電話(スマートフォン)の小型化は著しく、どんどん小さく、軽量化されているのです。会社や研究所などの巨大な空間にしか置けなかったパソコンが、小型化されたことにより、今や各家庭に1台あるような状態です。それによって私たちは、自宅にいながら世界中から必要な情報を得られるようになり、いつでもどこでも必要に応じて人とつながれるようになりました。情報処理や研究開発など、専門的な用途で使用されていたモノが、小型化によって人の生活における必需品の一つとなり、モノの可能性が広がった一例といえるでしょう。
3-2. 災害や医療の現場でも役立つ
モノの「小型化」は、医療分野や人が入れないような狭い所での作業を助けるといった面でも、想定されています。医療分野では、小さなロボットなどを体内に入れて、患部を治療するというものです。傷口が狭ければ、術後の回復も早く、人へのダメージを抑えられます。実用化には時間がかかるものの、とても興味深い研究です。
また、人が入れないような狭い所、危険な場所での作業を助ける用途としても使用できる可能性があります。たとえば、災害時に、壊れてしまった建物のなかに入り、生存している人を見つけ出す等の用途が考えられるでしょう。災害時の補助をするロボットなどはすでに存在していますが、より小型化されることによって、入り口はほとんど塞がっているような場所でも、中の様子を確認できます。これらは、モノが小型化されたことによって、今まで不可能だったことが実現可能になる例です。モノの小型化は、このような点からも大きなメリットがあるといえます。
-
4. まとめ
モノが小型化・軽量化されることは、今までは当たり前と受け入れられていたさまざまなものを省きます。そして小型化することによってモノの用途が無限に広がる可能性を秘めています。ものづくりで小型化を検討されている方は一度、「株式会社ファブナック」にご相談ください。製造のしやすさを考慮し、適切なご提案やアドバイスをさせていただきます。
